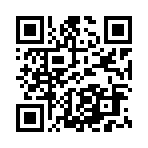2008年01月31日
区分所有法(マンション法)とは
マンションをめぐって生じる法律問題を解決する法的基準が、『区分所有法(マンション法)』です。
区分所有法(マンション法)は、次のようなことを規定しています。
① 誰が、マンションのどの部分に対して、どのような権利を持っている
か
② それぞれが所有するマンションの住戸(号室)と敷地との法律関係
③ マンションを誰がどのような手続きを経て管理するか
ですから、区分所有法(マンション法)を学ぶことによって、マンションのトラブルに対応できる知識を身につけることが出来ますし、また、トラブルの発生を未然に防ぐことも出来ます。
ちなみに、区分所有法(マンション法)は、③の「意見や利害の異なる多くの人が生活するマンション全体を誰がどのように管理するのか」という管理に関して、上の部分(管理者)と下の部分(管理組合・総会)だけ決まっていて、真ん中の部分の理事会の部分を何も規定していない法律です。
つまり、そこに好きなメニューを持ってきていいですよというスタンスで、法律は用意されているわけです。
で、その真ん中のために、 管理会社との「業務委託契約」や「管理規約」や「マンション管理適正化指針」がある訳です。
 マンション管理適正化法 4条には、管理組合の努力義務という条文があって、「マンションの一室を買って持ち主になった人は全員責任があります」という非常に重要なことが書かれています。
マンション管理適正化法 4条には、管理組合の努力義務という条文があって、「マンションの一室を買って持ち主になった人は全員責任があります」という非常に重要なことが書かれています。
管理組合が主体で 自分達のマンションを管理をしなければいけないとしているわけです。
区分所有法(マンション法)は、次のようなことを規定しています。
① 誰が、マンションのどの部分に対して、どのような権利を持っている
か
② それぞれが所有するマンションの住戸(号室)と敷地との法律関係
③ マンションを誰がどのような手続きを経て管理するか
ですから、区分所有法(マンション法)を学ぶことによって、マンションのトラブルに対応できる知識を身につけることが出来ますし、また、トラブルの発生を未然に防ぐことも出来ます。

ちなみに、区分所有法(マンション法)は、③の「意見や利害の異なる多くの人が生活するマンション全体を誰がどのように管理するのか」という管理に関して、上の部分(管理者)と下の部分(管理組合・総会)だけ決まっていて、真ん中の部分の理事会の部分を何も規定していない法律です。
つまり、そこに好きなメニューを持ってきていいですよというスタンスで、法律は用意されているわけです。

で、その真ん中のために、 管理会社との「業務委託契約」や「管理規約」や「マンション管理適正化指針」がある訳です。
 マンション管理適正化法 4条には、管理組合の努力義務という条文があって、「マンションの一室を買って持ち主になった人は全員責任があります」という非常に重要なことが書かれています。
マンション管理適正化法 4条には、管理組合の努力義務という条文があって、「マンションの一室を買って持ち主になった人は全員責任があります」という非常に重要なことが書かれています。管理組合が主体で 自分達のマンションを管理をしなければいけないとしているわけです。

Posted by kgw at 00:42│Comments(0)